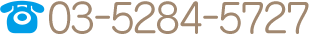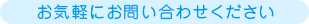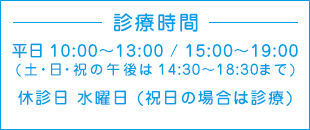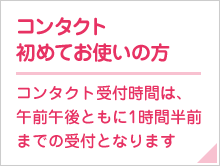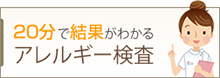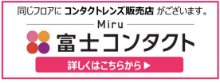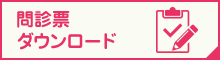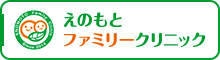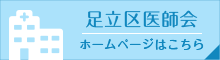円錐角膜について
2018.08.25更新
円錐角膜とは、角膜(黒目)が円錐状に前方に突出してしまう病気です。
円錐角膜は10代前半から発症することが多く、数千人に一人の割合で認められます。乱視の進行が早かったり、あわせたメガネやコンタクトがすぐにあわなくなる場合は、円錐角膜のこともあります。円錐角膜の場合、眼鏡やソフトコンタクトでは視力が十分に矯正できないため、ハードコンタクトで矯正します。また、ハードコンタクトの装用により、角膜が前方に突出することを予防するという治療の意味もあります。
中学生以上の方で、乱視の進行が早かったり、眼鏡やコンタクトがすぐにあわなくなる方や、円錐角膜が気になる方は眼科受診をお勧めします。